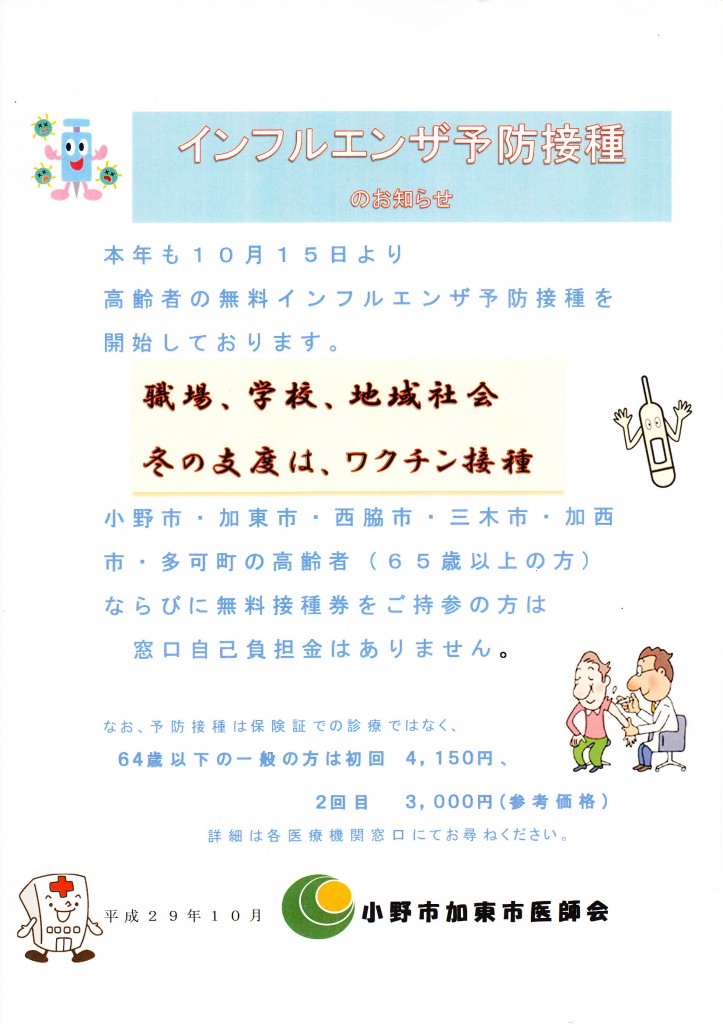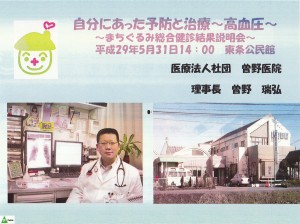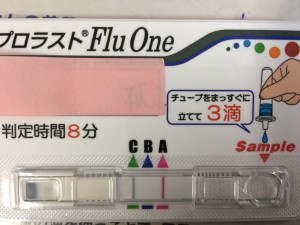2018年1月23日、日本イーライリリー株式会社と日本交通株式会社は、共同で「ライフスタイルに合わせた糖尿病の治療と対策セミナー」を都内において開催されました。
仕事上普段座りっぱなしの方々はなかなか運動の機会は少なく、糖尿病の対策及び治療についてどうすればいいか?良いアドバイスを頂いたと思います。
糖尿病とは
① 空腹時血糖 126mg/dL以上
② 随時血糖 200 mg/dL以上
③ HbA1c(ヘモグロビンA1c) 6.5%以上
上記3つのうち2つ以上該当すれば診断されます。
1つであれば糖尿病予備軍として要注意です。
糖尿病は治療して良くなっても、治療を中止したらまた悪化する継続的に治療が必要な病気です。糖尿病は血管の病気です。動脈硬化を起こし、血管を脆く、硬くさせます。
糖尿病は三大合併症(網膜症(失明になる可能性)、腎症(透析になる可能性)、神経障害(手足のしびれ、知覚低下など))を始め、脳、心血管障害、癌、認知症などの発症と大きく関り、決して油断できません!
糖尿病はⅠ型糖尿病とⅡ型糖尿病があり、Ⅱ型糖尿病の治療は主に食事療法、運動療法で行われ、不十分場合に薬物療法を行います。(Ⅰ型はインスリンの投与が必要です。)
特に薬物療法は飲む回数や飲み方は主治医とよく相談しなければなりません。低血糖(血糖の下げ過ぎ)、気分不良などの副作用にも注意が必要です。特にお年寄りは認知の低下などで上手く家族や主治医に症状を伝えることができないことがあり、不可逆的な脳障害などを引き起こすことがあり、要注意です。
食事療法は糖質、栄養の偏りに注意し、「単品・シンプル」「食事時間が不規則」、「炭水化物過多」などの問題のある食べ方を控えなければなりません。
「食事の残念サイクル」として「早食い→満腹感が少ない→もっと食べたい→間食どか食い→血糖値の乱れ→栄養バランスが崩れる→早食い」を管理栄養士の浅野氏が指摘しました。この「残念サイクル」を崩すためにはポテト、マカロニ、春雨、マヨネーズ系サラダを除く野菜を食事の最初に食べることです。外食時に①野菜を追加してベジファースト②単品よりも定食・おかず付き③調味料を追加しないと3つのポイントを指導しました。
外食対策としては、 たとえば立ち食いそば屋では、ワカメ、ネギ、卵のトッピングの追加、つゆと麺は半分残す覚悟で、おにぎり・いなり寿司の追加はダメ、麺はすすらずによく咀嚼するなど細かい点についてアドバイスを行いました。同じく牛丼屋では、丼よりも定食を選択し、野菜、トロロなどの小皿を足すこと、小盛を注文することなどを浅野氏が指導しました。コンビニでは、弁当ではなく、自分で定食メニューを作ることが提案され、一例としておにぎり、サラダセット、インスタントみそ汁で構成する工夫などが示されました。そのほか、肉を食べる場合は揚物、ハンバーグなどの加工肉ではなく、焼肉などのシンプルなものを、間食はヨーグルトやナッツ、スティック野菜などが勧められ、飲み物では「みえない糖」に注意し、スポーツドリンクや缶コーヒーは控えてもらいたいとアドバイスしました。
最後に浅野氏は外食5つのポイントとして、「(1)ダブル炭水化物はやめる(2)食事時間にリズムをつける(3)食事の最初に野菜を食べる(4)加工の少ない食材を選ぶ(5)間食は足りない栄養素を補給する時間」を示し、「食べないで我慢するのでなく、自分に合った食事を選ぶ力をつけてほしい」と説明しました。
中野 ジェームズ 修一氏(フィジカルトレーナー)が、運動でできる糖尿病予防について以下の通りアドバイスしました。
糖尿病を運動で予防するためには、大きな筋肉で多くの糖を効率的に使うことが求められます。そのため考案された運動では、負荷設定が少し高めにされ、筋肉量が多い太ももなど、下半身の筋肉を多く使用します。運動は、畳半畳程度で場所をとらず、5分程度ででき、スクワット、膝のアップを中心に9つの動作×10回で構成され、これを2セット行うものです。
中野氏は「運動は、一度習慣付けると長く続く。仕事の合間などにこの運動を行うことで、健康を維持してほしい」と期待を寄せました。